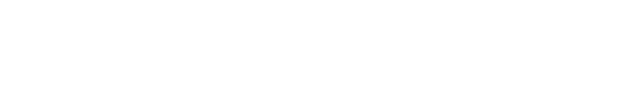糖尿病においても個別化治療というものはあるのでしょうか。
個別化医療とはあまり聞きなれた言葉ではないかと思いますが、患者さん一人ひとりの体質、生活習慣、環境要因、遺伝情報などを考慮して、最適な治療や予防策を提供する医療のアプローチです。がん治療における遺伝子解析、薬の代謝に関する遺伝子検査などが有名ですが、個別化医療のメリットは、治療の効果を最大にして、副作用を最小にする、不必要な治療の回避する、医療資源の効率的な活用するなどがあります。
糖尿病に関しての個別化治療としては、各人で肥満のタイプ、インスリン抵抗性、インスリン分泌不全などと病態が異なり、生活習慣も異なりますのでそれぞれの病態や生活習慣に応じて、治療戦略が個別に設計されるということになります。 薬もそれぞれに適した薬剤(例えばメトホルミン、SGLT2阻害薬、GLP-1受容体作動薬など)を選択するという風になります。
具体的な報告をみていきましょう。
2018年、Ahlqvistらスウェーデンの研究グループは、ANDISという研究でスウェーデンとフィンランドの合計14.755人において、糖尿病診断時における体格指数(BMI),年齢,診断時のHbA1c,HOME-β,HOME-IR,抗GAD抗体の6つの情報を用いて人工知能(AI)を用いてK平均クラスタリングという手法により5つのクラスター(群)を同定しました。
それによって新しい糖尿病分類の可能性が出てきました。それは
1群 自己免疫性糖尿病 従来の1型糖尿病
2群 重度インスリン欠乏糖尿病
3群 重度インスリン抵抗性糖尿病
4群 軽度肥満関連糖尿病
5群 加齢関連糖尿病
の5つのクラスター(群)です。
高血糖の程度はHbA1cで
インスリン分泌能はインスリンの値と血糖値で計算されるHOME-βという指標で
インスリン抵抗性は同じくインスリンの値と血糖値で計算されるHOME-IRという指標で
自己免疫性は抗GAD抗体という抗体で判定します
体格指数(BMI)は体重(Kg)/身長(m)x身長(m)で表せます。
各群(クラスター)を説明していきます。
1群 自己免疫性糖尿病は従来の1型糖尿病のことです。
GAD抗体陽性、インスリンが枯渇、高血糖が著しい、若年発症が特徴です。
2群 重度インスリン欠乏糖尿病は1型糖尿病でないものの
高度なインスリン欠乏、著しい高血糖を呈しますが、GAD抗体は陰性です。
3群 重度インスリン抵抗性糖尿病は
高度な肥満、重度のインスリン抵抗性、脂肪肝があるが特徴的です。
4群 軽度肥満関連糖尿病とは
肥満は軽度でインスリン抵抗性も軽度です。
5群 加齢関連糖尿病は
高齢で発症し、痩せ型でインスリン分泌不全は軽度です。
1~4群は非高齢の発症で罹病期間が長いのが、5群は高齢発症で罹病期間は短いのが特徴です。
クラスター分類すると糖尿病の合併症、併存症の推定に有用です。具体的には
1群 自己免疫性糖尿病 従来の1型糖尿病では
網膜症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎臓病、高血糖緊急を起こしやすいです。
2群 重度インスリン欠乏糖尿病
これは1群と同じです。
3群 重度インスリン抵抗性糖尿病においては
脂肪肝、糖尿病腎臓病、冠動脈疾患、脳卒中、心不全といろいろ起こしやすいのが特徴です。
4群 軽度肥満関連糖尿病は
合併症、併存症が少ないのが特徴です。 脂肪肝があります。
5群 加齢関連糖尿病
高血糖とは直接関係ない合併症が多いです。 フレイルとか骨折、転倒 冠動脈疾患 軽度認知障害などです。
分類することによって将来の合併症発症のリスクを知り、対策を考えることが出来るのです。
また、クラスター分類から糖尿病の治療を考えることもできます。
1群 自己免疫性糖尿病 従来の1型糖尿病ですので当然強化インスリン療法です。膵移植もあります。
2群 重度インスリン欠乏糖尿病では早期のインスリン補充が大切です。
3群 重度インスリン抵抗性糖尿病では包括的治療(食事、運動、薬物)、体重管理が重要です。重症では肥満手術です。 薬物としてはメトホルミン、SGLT2阻害薬、GLP-1製剤が優先されます。
4群 軽度肥満関連糖尿病 食事、運動、体重管理が主体で薬物としてはメトホルミン、SGLT2阻害薬、DDP-4阻害薬です。
5群 加齢関連糖尿病では包括的治療(食事、運動、薬物)です。低血糖やポリファーマシー(多剤併用)に気を付けるが大切です。
などが考えられます。今後これらのことがよく実証されていくでしょう。
さらにこれとは別の研究でもどの薬物を優先するかについての示唆を与えてます。以下は細かいので読み飛ばしてもらっても結構ですが。
ADOPT研究、RECORD研究では加齢関連糖尿病クラスターにSU薬、重度インスリン欠乏クラスターにチアゾリジン薬が有用であった。
血管疾患発症を結果としたDEVOTE試験、LEADER試験、SUSTAIN-6試験のデータを用いた検討では、重度インスリン欠乏糖尿病型は心血管イベントが多いことが示されています、またインスリングラルギンが有用である可能性がORIGIN研究で示されてます。
オランダとスコットランドのかかりつけ医に通院中の9.199人において、ベースラインの年齢、BMI、HbA1c、HDLコレステロール値、Cペプチド値により5つのクラスターに分類すると、重度のインスリン抵抗性クラスターにおいて、軽度の心筋梗塞のリスクが1.72倍に上昇していた。重度のインスリン欠乏クラスターでは発症から10年で25%以上がインスリン治療を受けていた。
2.652人の中国人集団の電子カルテデータでは、加齢関連糖尿病クラスターに比較して重度インスリン欠乏クラスターでは糖尿病性腎臓病のリスクが高く、重度インスリン欠乏では網膜症のリスクが高かった。
などなどです。
遺伝子解析を用いた個別化医療の研究も進んでいます。
ACCORD研究という有名な研究があります。 これはHbA1cでみた強化療法での治療経過を4つのグループに分けた研究で、強化療法群全体ではむしろ心血管疾患が増えてしまってパラドキシカルな結果となってしまったものです。 しかしながらHbA1cが6.2%と強化療法に非常によく反応したグループでは逆に心血管疾患の発症が抑制され、その遺伝子的背景が示されました。
250万人分の遺伝子情報を含む136の大規模ゲノム解析の結果を統合して調べた研究では、1,200あまりの遺伝的要因が2型糖尿病発症に関係してることが分かりました。それらの2型糖尿病に関連する遺伝子要因を8つのクラスターに分け、2型糖尿病の合併症のリスクへの影響を調べました。 その中で肥満にかかわる遺伝的要因のクラスターの人は、透析を必要とする慢性腎臓病、冠動脈疾患、末梢動脈疾患などの合併症を発症しやすい傾向がありました。肥満にかかわる遺伝的要因のリスク値が高いひとは合併症のリスクが高いため、体重が減りやすく合併症リスクが下るSGLT2阻害薬やGLP-1受容体作動薬を早くから積極的に使う可能性が考えられます。
またインスリン分泌を抑え、プロインスリンが上昇する遺伝的要因のリスク値が高い人は、合併症のリスクが高くなかったです。 増殖糖尿病網膜症については、2型糖尿病そのものの遺伝的リスク値が高い人に発症しやすい傾向がありました。
まだ糖尿病の個別化治療として完成されたものはありませんが、これらの知見は、患者さん一人ひとりの特徴を考慮した糖尿病治療の参考になるかと思います。遺伝子情報を得ることは出来ないにしても、皆さんもどのタイプ(どのクラスター)に属するかを考えてみられては如何でしょうか。
遺伝子情報を含めた更なる糖尿病の個別化医療の実現を期待するものであります。