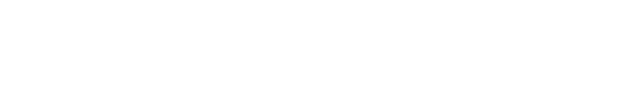糖尿病とカリウム
体内にあるミネラルでナトリウムについては高血圧、腎臓病、心臓病の関係でどちらかというと悪者扱いでご存じの方は多いかと思います。が今回はカリウムについてお話ししたいと思います。カリウムは、人間の健康にとって非常に重要なミネラルですし、糖尿病との関係も深いのです。
ナトリウムが細胞外の血液の主なミネラルであるのに対して、カリウムは細胞内の主なミネラルでして、細胞の中に約98%が存在しています。残りのわずか2%が主に血液中に存在することになりますが、しかしその中の多い少ないが大変問題となります。
カリウムは、体内の生命維持活動に欠かせないミネラルで次のような効果があります。
- 細胞の浸透圧を調整する
- 水分を保持する
- 神経刺激を伝達する
- エネルギー代謝に関与する
- pHを維持する
- 心臓や筋肉の機能を調節する
- 細胞内の酵素反応を調節する
- ナトリウムを排泄して血圧を下げる
などです。血圧を下げる栄養素としても有名ですね
これらの目的を果たすために、体外から摂取したカリウムは腎臓の働きにより、血液中の濃度が3.6~5.0 mEq/Lと一定になるように調節されています。この値より低くても、高くても体にとって不都合なことが起こってしまいます。例えば腎機能に異常がある場合、カリウムが血液中に過剰となり体に悪影響を及ぼします。
カリウムの値が下がってしまう低カリウム血症は麻痺、けいれん、あるいは致命的な不整脈を引き起こし得ます。初期の症状としては、手や足のつりや、こむら返りが挙げられます。
カリウムは神経や筋の機能に不可欠な細胞内と外に発生する電気の差に寄与してまして、この変化に最も影響を受ける臓器は筋肉と心臓です。そのため脱力感、筋力低下、食欲不振、骨格筋の麻痺、不整脈などを来してしまうのです。
カリウムは動物性食品や植物性食品に豊富に含まれていますので、通常の食事ではほとんど欠乏はみられません。低カリウム血症になることはありません。
しかし、激しい嘔吐や下痢の場合や高血圧症に使われる降圧利尿剤の長期使用の場合などでは、カリウムの排泄量が増して欠乏することがあります。また多くの利尿薬はカリウムを排せつする作用があるため、副作用として低カリウム血症になることがあります。漢方薬に含まれる甘草(かんぞう)という成分にはグリチルリチン酸が含まれ、これが低カリウム血症を引き起すこともあります。 高血糖の方がインスリンを使用すると、低カリウム血症になることもありますがこれはまれです。
カリウム欠乏、低カリウム血症は特に糖尿病を持っておられる方に多いということはありません。しかし何か症状的に気になる方は血液検査のカリウム(K)の項目を見てみると良いでしょう。
次にカリウム過剰、高カリウム血症について考えてみましょう。この場合は糖尿病を持っておられる方にしばしばみられるといってよいでしょう。
カリウム値が高すぎると出る症状としては
- 手足、唇のしびれ
- だるい、胸が苦しい
- ろれつが回らない
- 意識がなくなる、などがあります
- ひどい場合には不整脈をおこし、さらには心肺が停止してしまいます
高カリウム血症になりますと、筋肉や心臓の収縮が調節できなくなり、手足のしびれ、麻痺や心電図異常などの症状が現れ、重篤な場合は心停止を起こすこともあるのです。
ではカリウムが上がる原因は何でしょうか?
カリウムは多くの食品に含まれていますが、腎機能が正常で、特にカリウムのサプリメントなどを使用しない限りは、ふつうは過剰摂取になる心配はないと思われます。ですので日本人の食事摂取基準(2020年版)においても上限量は設定されておりません。ではどういう場合で上がるのでしょうか。
まず、第一に糖尿病の合併症の腎症が進行すると腎機能が低下し、カリウム排泄が十分出来なくなり高カリウム血症になることがあります。
次に糖尿病の併発症であります高血圧や腎臓病、心臓病の治療薬として使われるアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)やACE阻害薬(ACEi)を内服されている患者さんは高カリウム血症を引き起こしやすくなります。
しかし合併症や併発症もない一般の糖尿患者さんでも時々みられるのはアルドステロンというホルモンの低下による高カリウム血症です。一般的な臨床では特に原因のない高カリウム血症として扱われることになります。
このような場合、果物や生野菜の摂取を制限されることもあります。その代わりとして、しばしば缶詰の果物や、ゆでこぼしたり、水にさらした野菜が勧められることもあります。カリウムは水溶性で、煮たりゆでたりすると水に溶け出すからです。 カリウムは、藻類、果実類、いも及びでん粉類、豆類、肉類、魚介類、野菜類などに多く含まれます。生鮮食品に多く、加工や精製が進むと含量は減少します。
ここでカリウムを多く含む食品を列挙してみましょう。
1.野菜
野菜のうち、特にいも類やかぼちゃには多くのカリウムが含まれています。ほうれん草、トマト、ポテト、さつまいもなどに多いです。特にトマトジュースにも、200mlあたり546mgと多くのカリウムが含んでいます。
2.果物
バナナ、アボカド、オレンジ、キウイなどに多く含まれます。
3.豆類
大豆やおから、納豆、きな粉などは大量のカリウムを含みます。
4.肉類、魚類
カリウムを多く含みます。牛肉、豚肉、鶏肉、あじ、あゆなどです。
5.海藻類
やはり多くのカリウムを含みます。
カリウムの一日の摂取目安量は、成人男性で3,000mg以上、成人女性で2,600mg以上です。ですがカリウムはいも類や海藻類など、身近な食べ物に豊富に含まれているため、基本的に普段の食事で不足することはありません。
また逆に、カリウムを過剰摂取してしまうことも普通の食生活をしていればまずないといってよいでしょう。多くの食品に含まれてはいるものの、腎臓が正常に働いていれば排泄されてしまうため、過剰摂取になることはありません。
しかし以下に当てはまる場合は、カリウムを過剰摂取してしまう可能性があります
先にあげました腎臓の機能が落ちているとか、ARB やACEiを内服されてる方とか、アルドステロンの低下してる方はカリウムがたまりやすくなっています。その場合は果物を少なくしたり、野菜を細かく刻んで火を通し、ゆで汁を捨て水気をしっかり切ったりすることでカリウムの摂取量を減らすことが可能です。
しかしここで重要なことは野菜にしても、果物、大豆にしても重要な栄養源であり、摂取を厳しく減らすことはできません。野菜、果物摂取が少ないほど心血管イベントが増えるという報告もあります。
さらに最近の研究では、心不全あるいは蛋白尿のある慢性腎臓病患者において、カリウムを上げてしまうARB、 ACEiの中止あるいは減量は、死亡率および有害な心血管系イベントを増加させてしまうという報告があります。このような場合においては血清カリウムをコントロールしつつこの薬を使用することが大切ということになります。
これらの場合、カリウム吸着剤という薬剤の使用も大切なものとなってきます。カリウムを腸管内で吸着して腸から吸収されるカリウムを減らしてしまう薬剤です。従来は飲みにくかったり便秘という副作用が出ることもありましたが、最近は飲みやすて便秘も起こさないタイプの薬も出てきてます。
皆様の中でもしカリウムが高いと言われた方がおりましたら、これらの薬剤をうまく利用して緩いカリウム制限位で充実した食生活を送ってもらいたいものです。