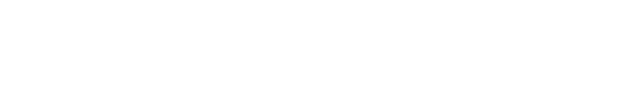運動の疑問?
糖尿病があって運動をしなければならないと思っていてもなかなか始められないか方、やり始めたいがどうのような運動をどの程度やったらよいかわからないという方は多いと思います。すでにやり始めている方でもいろんな疑問をもっているかと思います。
今回はこのような疑問をエビデンスをもとに考えてみます。
運動は色んなやり方がありますが、まずは少しでも良いから始めてみることです。運動療法はたくさん時間をかけて、しっかりやらないとだめだと思ってる方も多いかと思います。しかし、少ない時間でもその効果かあるという報告は多いです。何でもよいから、少しでも良いからやってみることが大切です。それなりの効果はあるものです。
運動する目的は何でしょう?
1つは血糖を下げることです。糖尿病のある方はまずこれを期待してます。
2つ目は体重を減らしたい、あるいは筋力を維持していたいです。一般の方では普通これを第一に期待いでしょう。
3つ目は心臓、血管の疾患リスクを下げる、癌の発症率を下げる、認知症を予防するなど将来の健康を保つことを目的にします。
これらのことはすべてエビデンスがあり運動の確たる効果と言えます。
運動にはどんな種類があるのでしょうか?
坐位時間の短縮、歩行、中高強度有酸素運動、筋力トレーニングです。
1日の坐位の時間を減らしたり、連続した坐位時間を減らすとかも運動療法として大切です。
坐位時間とはテレビを見たり、本を読んだり、パソコンを見たり、ソファーに横になっている時間のことです。
歩行は有酸素運動の一つですが入りやすく、また多くの疫学的研究がなされエビデンスが豊富です。
強度の強い有酸素運動は単に歩くのと比べてよりエネルギー消費が高く、血糖値も下がり、体力もつきます。
筋トレは筋肉に負荷をかけ、筋力をつけたり筋肉を増やしたりします。各年代で有効ですが、高齢者には特に有効です。減量には必須と言えるでしょう。
他にバランストレーニングがあります。あえて不安定な姿勢をとることによって転倒防止に役立てます。
運動を始める方はどの運動から始めて良いですし、少量からでも大丈夫です。またすでにかなり歩いている方でも筋トレを追加すれば更に効果を得ることができます。組み合わせは自由です。
何歩、歩いたらよいですか
歩行の運動量を測るのは歩数が適切です、距離とか時間ではなく歩数なら比較検討ができるからです。翌1日1万歩歩きましょうといわれていますが、特に科学的に根拠のある数字ではないようです。健康づくりのための身体活動.運動ガイドでは成人では1日8,000歩以上、高齢者では6,000歩以上を目標とすることが勧められてます。これは歩行と死亡率との関係を見た疫学的研究からの結論です。成人では8,000~10,000歩、高齢者では6,000~8,000歩までは死亡率の低下がみられましたがそれ以上では横ばいだったという結果でした。ただし糖尿病のある方にとってはそれ以上の歩数歩けばより血糖は下がりやすくなることも事実です。
中高強度有酸素運動とは
中高強度有酸素運動と呼ばれる運動ですがランニング、サイクリング、スイミングなどがあります。すこしハードルが高くなりますが心拍数を上げる運動も重要です。週3日以上、週150分以上が目標とされてます。難しい方も多いと思われます。しかし最初からあきらめずに週10分からでどうでしょうか。徐々に時間を延ばしていけると良いですね。
筋トレの目標は?
週2~3日、1セット当たり10~15回、1日2~3セットが勧められてます。連続した日では行わないことが推奨されます。これは筋トレによって生じた筋肉の損傷を回復させる時間が必要なためです。しかしそれ程強度な筋トレでなければ習慣として毎日やるのも良いかと思います。
柔軟性トレーニングとバランストレーニングと筋肉トレーニングを組み合わせた複合運動というのがあります。具体的にはヨガ、太極拳、ピラティス(良くは知りませんが)などがあります。これらの運動は血糖値を改善したり、身体能力を高めるということが報告されています。集団でやる場合もあり、1人でもでき、動画を見ながらやるということもできます。自由にできますしレジャー性があるのも利点です。週に2~3回はやってみたいものです。
運動は何から始めてもよく、運動量もご自分の都合、好みに合わせてやっていけばよいのですが、多くの方に選ばれるのは糖尿病があってもなくても歩行です。いわゆるウオーキングです。誰でも手軽に始められますし、特別な器具や技術を要しないからです。このことは逆にウオーキング以外の運動は厳しいという現実を示しているのでしょう。次に多いのは自転車で、その次は筋トレです。当院でも同様の傾向です。筋トレは短時間で出きますので、時間のない方には最適です。“時間がない”は運動できない理由のナンバーワンです。また高齢者には特にお奨めです。
高齢者にお奨めの自宅でやる筋トレは下肢筋力やバランス能力を向上させ安全で効果的な運動方法です。高齢者の転倒防止や生活機能の改善に寄与するものです。スクワットや腹筋、カーフレイズ(つま先立ち)などがあります。自宅でできてお金もかからず安全にできます。
他に器具を使うトレーニングはダンベルやバーベルがあります。高度なものはバーベルスクワット、ベンチプレス、ダンベルフライあるとのことですがジムが必要なことが多いのが欠点です。更にマシントレーニングとなると完全にジムが必要となります。いずれにしても筋トレは血糖を下げるという報告があります。できるものやってみると良いでしょう。一回の筋トレでも効果はあります。
以下ではQ&A形式で運動に関する種々の疑問を考えてみます。
肥満のある糖尿病の方にお勧めの運動は?
有酸素運動と筋肉トレーニングの併用が効果的です。両者の併用が体重減少、インスリン感受性の改善、心肺機能の向上に役立ちます。有酸素運動だけでは体重減少の効果は限定的です。
腰痛に1番良い運動は?
ピラティス、体幹安定運動、筋トレ、有酸素運動ともに効果的です。 が、ピラティスが1番良いとの報告があります。これらの運動はマッサージなどよりも効果的と言われてます。安静にしすぎるとかえって良くないこともあります。
腹部の皮下脂肪を減らす運動は有酸素運動と筋トレどちらが良いでしょうか?
有酸素と筋トレとでは効果に差はなかったと言います。従ってどちらでも良いですが、やはり併用が1番です。
血糖を下げる運動は有酸素と筋トレどちらが良いでしょうか?
どちらでも構いません。 有酸素運動は脂肪を燃焼し心肺機能を高めエネルギーを消費して血糖を下げます。筋トレは筋肉量を増やし、インスリンの効きを良くします。また筋肉による血液中の糖の取り込みを良くして血糖を下げます。さらに両者の併用で血糖管理の相乗効果が期待できます。週に3~5回の有酸素運動(ウオーキングやサイクリング、ジョギング)と週2~3回の筋トレをお奨めします。
運動はインスリン分泌能力を改善しますか?
改善します。膵β細胞の負担を減らし、再生と増殖を促します。
運動は筋肉や肝臓のインスリンの効きを良くして、少ないインスリンで血糖を下げ膵臓の負担を減らします。その結果膵β細胞の負担が減り疲弊やアポトーシス(自然死)が減ります。 また運動することによってGLP-1やFGF23といったホルモンが分泌され、これがβ細胞の増殖を促します。さらに運動は膵島(β細胞の集まり)の炎症を抑えたり、酸化ストレスを軽減させます。その結果インスリン分泌の機能を改善させます。運動はインスリンを分泌させると言っても良いでしょう。
運動は減量に効果的でしょうか?
効果はありますが限定的と言うことです。 減量効果は週150分以上の有酸素運動でみられ、それは運動時間とともに増します。しかし食事療法と比べると減量に対する効果はあまり大きくないです。運動による消費エネルギーは意外に少なく、食事によるエネルギー摂取量の調節の方が減量に結び付きやすいからです。しかし運動が全く無意味ということはなく減量後の体重維持や肥満症関連の健康障害の改善に役立ちます。
運動は食後にするべき?
食後に運動をすることで、食前に運動することと比べて明らかに食後の血糖が抑えられることが示されています。特に食後の早いタイミングでの運動が推奨されます。細かく言いますと食後血糖値がピークに達する20分前から開始すると効果的に血糖上昇を抑え、インスリンの過剰分泌を抑制できます。一般的には食後30分位に開始できると良いでしょう。しかし食後すぐに運動しますと消化管には負担がかかります。消化管の機能には個人差がありますので、自分のペースでやると良いでしょう。食前の運動でもしないよりはやったほうがはるかに良いということは知っておきましょう。
高強度の運動を短時間するのと、低強度を長時間するのではどちらが良いでしょうか?
効果は変わらないようです。 肥満を伴う糖尿病においては、エネルギー消費量が同じであれば体重、HbA1cに対する効果は同等であるということが示されてます。時間のある方は低強度を長時間で、時間のない方は高強度の運動を短時間という選択もあります。
仕事でよく体を動かしますが、休日も運動するべきでしょうか?
した方がよいという報告が多いです。 その理由は仕事で体を動かすことは有益ですが、その多くは軽度から中等度の運動で高強度の運動は不足しがちですということと、仕事での活動とは異なる筋肉を鍛える機会を得られるということです。
以上雑ぱくな話でしたが少しでも運動の疑問を晴らして、運動にさらに興味を持って開始されたり、持続されたりすることを希望いたします。
参考文献: 糖尿病運動療法154のエビデンス 中外医学社
今度こそできる糖尿病運動療法 サイエンス&プラクティス 医歯薬出版株式会社